それじゃ……ラ・ラ・ランドの考察記事だけど……あれ? 主は?
今回は姿を見せんようじゃな。メモ書きだけ残して、あとはわしらに任せるらしい
カエルくん(以下カエル)
「デジモンやヤマトの公開週でもあるしねぇ……そっちに行ったり、あっちに行ったりで忙しいのかな?」
亀爺(以下亀)
「いやいや、案外自分がノレなかったから、批評記事にやる気がないだけかもしれんぞ」
カエル「それじゃ、今回は考察の記事だけど……今回はその性質上、ネタバレ全開で書いていくのね?」
亀「そうじゃの。
ネタバレなしの感想記事を読みたい人は、ぜひこちらを参考にしてほしい。
こちらではチャゼル監督についてや、アカデミー賞選考委員や批評家などが絶賛するのか、簡単に書いていていこう。
もちろん、こちらでもその理由は書いていくぞ!」
カエル「じゃあ映画批評スタート!」
スタートのうまさ
本作は何と言ってもスタートが素晴らしいよね!
この映画はスタートに全てが詰まっておる
亀「そして、あのシーンだけでも、観るものが見たらその多くのメッセージに気がつくんじゃよ」
カエル「え? それってあの冒頭のミュージカルシーンじゃなくて?」
亀「違うの。まず、昔のような白黒のロゴが出て、それが少し小さめじゃったろ? そして比率を現代に近づけることで、本作は物語が始まる。
これは『過去の映画たちに捧げる』というメッセージを含んでおる。この冒頭のメッセージだけで、映画を……特に古い映画を愛する者からすると、ノックアウトされるわけじゃ」
カエル「へー! なるほどね!」
亀「本作が多くの批評家から高評価を得るのは、こう言った『映画が好きならば分かるはずのメッセージ』が詰まっているからじゃな。
そこからナレーションが流れて、渋滞する車のへとカメラは降る。これは50年代の映画などに多い演出じゃの。古い映画が好きな人間であれば、これだけで『面白い!』となること間違いなしじゃよ」
カエル「そんなメッセージ溢れているんだね」
亀「今作はそのような『演出で語る』ということが多いからの。物語を追うだけでは、この映画の本当の意味というものを見失ってしまうからの」

冒頭のミュージカルシーンだけでわくわくする!
(C)2016 Summit Entertainment, LLC. All Rights Reserved.
渋滞からのミュージカル
圧巻のミュージカルシーンだよね! 本当は3カットをうまく編集しているようだけど、約5分弱かな? はありそうなロングカットのミュージカルシーンになっていたよね!
あのシーンは非常にうまいと感じさせられたの。
亀「ミュージカル映画で大切なことは『現実を忘れさせる』ということじゃ。これはミュージカルに限らず、映画……というよりも物語全てに言えることかもしれんが、ミュージカルはその要素の重要性が他の映画に比べて大きい。
当然のようにミュージカル映画は突然踊りだしたり、歌い始めたりする。それが演出として楽しかったり、大きな意味を持つのじゃが、これをリアリティを持って安易に取り入れてしまうと、非常に危険なわけじゃ」
カエル「突然歌って踊り始める人なんて、はっきり言ってしまえば異常者だもんね……」
亀「音楽演奏が魅力的な映画というのはたくさんある。例えば『バック・トゥ・ザ・フューチャー』や『シング・ストリート 未来へのうた』などがあるが、あれは作品世界と直接リンクしたまま演奏を始めるから、特に大きな違和感はない。
じゃが、ミュージカルというのは現実的に見せては絶対にダメじゃ。むしろ、その現実を忘れてみんなでその音楽と共に体を揺らすような演出というのが大事での。作品世界とミュージカルパートは、ある程度切り離さなければいかん」
カエル「ふむふむ……」
亀「じゃから『渋滞という日常』をまず見せる。そこでイライラする空気感などを共有した後に、それを吹き飛ばすような『理想の姿=映画の世界』へと没頭させるわけじゃ。
それが爽快であればあるほど、そして大規模であればあるほど、観客は現実の世界を忘れて映画の世界へと没頭することになる。だからあれほどの長回しで、大規模なものをにする必要があったんじゃな」
カエル「なるほどねぇ。このブログでは『セッション』の時もスタートがうまいって褒めていたよね」
亀「さらに言うと、この映画は『映画を語った映画』でもある。じゃから、あまりにも現実とかけ離れた映画にすると、映画は現実と縁がないことになり兼ねんからの。
その意味でも『現実の象徴=渋滞』と『映画の象徴=ミュージカル』の魅せ方というのは抜群にうまい」
冒頭の意味
さて、カエルはあのシーンからどのような印象を受けたかの?
え? 楽しいなぁって思ったけれど……
亀「それでは批評にならんじゃろうが……
あの渋滞で並ぶ車の列というのは色々な解釈ができるの。
わしはLAに向かう車の列=数々の映画達という説を唱えてみるかの。つまり、あれはそれまでの歴史上、たくさん存在した映画達のモチーフであり、それがあの明るい色の服を着た俳優達が踊ることによって『映画の世界へようこそ!』という意味があるの。
さらに言わせて貰えば、スタートの演出や、LA LA LANDという明らかにハリウッドを意識したタイトルなどを総合して考えてみると……この映画は『これから映画について語るよ』というメッセージも含んでおるじゃろうな」
カエル「歌詞も『夢を追うことは素晴らしい!』みたいな歌だしね。打ちひしがれた日も新しい朝が訪れる……みたいなさ」
亀「そのLAにたどり着くことができなかった役者やスタッフ、さらに言えばアイディアなども含めた、様々な映画達の象徴が踊りだすというのがあの冒頭の意味じゃろうな」
色彩のマジック
やっぱり、ミアのアップのシーンは圧倒的だったよね! あそこでさ、ミアの演技が本当に素晴らしいことの証明にもなっていて……」
わしが語りたいのは、ここではミアの……エマ・ストーンの演技ではないの
カエル「えー? じゃあこの顔のアップで何を語るのよ?」
亀「本作は色彩のマジックが素晴らしい。
例えば、このミアの演技のシーンというのは壁も服も青に統一されておる。するとどうなるか?
青という色は寒冷色であり、リラックス効果がある色でもある。青色を見るだけで集中力が上がったり、最近では蛍光灯を青系のものにするだけで犯罪率が減少するという実験データも有名じゃの。
このシーンではこの青が効果的に使われておるが、それはその前のミュージカルシーンで興奮気味になったテンションを、一度沈静化させるという意味もある」
カエル「色彩の心理効果から考えても効果的なんだね」
亀「さっき、カエルは『ミアの演技が素晴らしい!』といったじゃろう? もちろん、エマ・ストーンの演技力もあるのじゃが、色彩のマジックにより観客は画面に釘付になるように促されておる。
あれが真っ白な部屋であったり、真っ赤な部屋であれば全く同じ演技であっても受ける印象は違うはずじゃ。
さらに言うと、あれは悲しい場面の演技ではあったが、青色のような寒冷色には気持ちを落ち着かせる効果の他にも、悲しい気持ちを助長させることもある。そのような印象を狙っての演出じゃろうな」

青色が印象に残る場面。そしてより一層シャツの白が目立つ
(C)2016 Summit Entertainment, LLC. All Rights Reserved.
汚れたシャツ
いろいろと考えられているんだね……
そしてそれは汚れたシャツにも現れている
亀「ミアはオーディションで失敗し、1人涙目になりながら家路につくことになる。その時、廊下で待機している他のライバルたちはどうじゃった?
多くが同じような白いシャツを着ていたじゃろ?
結局のところ、あのシーンでは同じようなシャツを着ているミアの演技力は他の女優と大差ないということでもある」
カエル「しかもそのシャツが汚れているわけだからね」
亀「1人だけ汚れたシャツを着ているというのは『ケチのついた演技』という演出でもあるの。
ここの解釈も多様なものがあるが、わしは『エマの演技が他のオーディション相手とあまり変わらない』もしくは『少し落ちる演技をしてしまっている』という風に解釈する。
他にもこの視点で見ると面白いのが、セバスチャンの服の色じゃ。いつもは白いワイシャツを着ているにもかかわらず、あの流行のバンドに入って成功していくと、シャツの色は黒くなるじゃろ?
それで本当の気持ちを表しているということも言えるわけじゃな」
カエル「結構シャツの色とかでも色々わかるんだね……」
亀「この映画は情報量が多いから、どこの描写にどんな意味があるかと考察しながら見ていくのも楽しいの」

黒い服になるセバスチャン。ずっと白いシャツだったのに……
(C)2016 Summit Entertainment, LLC. All Rights Reserved.
街の風景など
そして鮮やかな色彩のドレスをまとった女性たちのミュージカルシーンがあり、ここで2人は本格的に出会うわけだね
この時壁に描かれておった壁画に人がいっぱいいたじゃろ? あれは『映画の観客』を意味している。
亀「では、その観客が描かれた店の中に入ったということは何を意味していると思う?」
カエル「えー? やっぱり映画がどうとかって話なの?」
亀「まあ、そうじゃの。
その前のミュージカルパートでは『誰かを探そう』とか『別の私に会いたい』という歌詞が出ておった。
これは考えてみるとあのお店の場面に入ったということは『物語の舞台に飛び込んでいった』ということでもある」
カエル「そこで2人は出会って、物語は進行していくわけだもんね」
亀「この風景などでいうとロサンゼルスの街並みであったり、その撮り方なども古い映画を意識しておったの。
街の中を散策しているとロケをしている場面があるなど、様々な風景に溢れている。あの脚立を持って歩く人々というのは、多くの映画の中でも出てくる描写じゃ。最近わしが見た中だと『バンド・ワゴン』の中でも脚立はちょっとした役割を果しておった」
カエル「『雨に唄えば』もそうだけど、当時の映画製作場面には必ずといってもいいくらいに、登場回数が多いアイテムでもあるよね。それだけ高所作業が多かったということでもあるんだろうけれど」
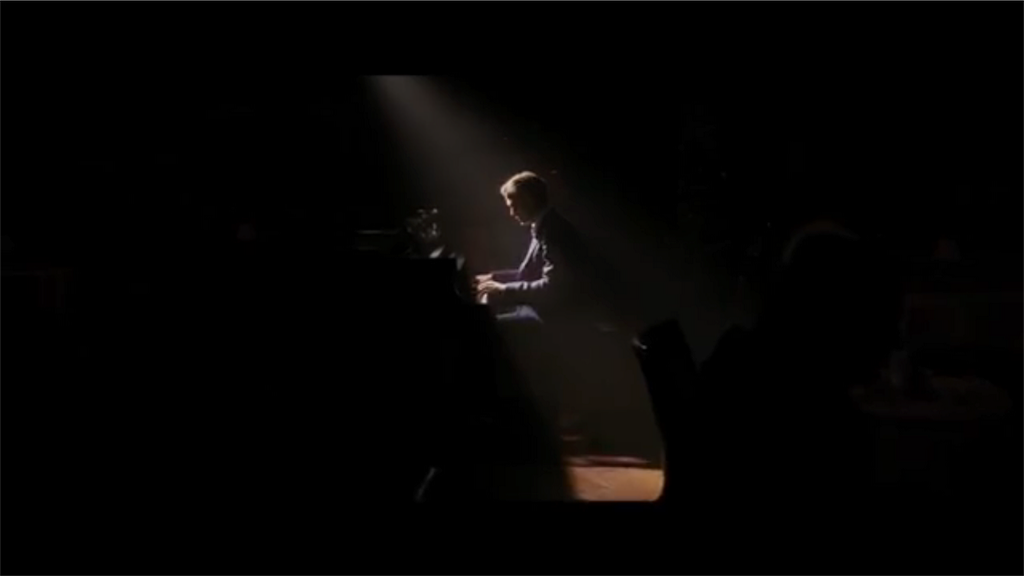
2人が初めて出会った場面。美しい。
(C)2016 Summit Entertainment, LLC. All Rights Reserved.
古い映画を思わせるものがいっぱい
ミアの壁に貼ってあったのもイングリット・バーグマンのポスターだし、セバスチャンもたくさんの古いスターに関連するグッズを集めていたね
それも年代を考えると少し古すぎるの。
亀「現代の女性であれば、イングリット・バーグマンよりもナタリー・ポートマンなどの方が憧れる対象としてはわかりやすい。日本人で言えば……そうじゃな、若い女優志望の女の子が原節子や高峰秀子に憧れておるようなものじゃからな。
もちろん、それはそれでおかしなことではないが、あまりにも時代が古すぎるような気もするの」
カエル「そういえば時代設定のお話がなかったけれど、これって現代のお話ってことでいいのかな?」
亀「……おそらくそれでいいはずじゃ。オーディションシーンも現代のようであったし、ジャズが時代遅れになるというのも現代の問題を提起しておるようにも思うしの。
まあ、それが主を興ざめさせた理由の1つなのじゃろうがの」
カエル「え? どういうこと?」
亀「さすがにこれだけ古い映画に関係するものが多いと、それだけで『賞レースの審査員に対する媚び』のようにも思えてくる。例えば日本において黒澤明や小津安二郎の映画をモチーフにしたシーンが出てきたら、そうそう簡単に否定することはできないからの。
それをこれでもか! と入れてきたことで、映画に詳しければ詳しいほどに誰も否定できない映画を作ろうという意図が見えてきてしまったの」
カエル「……それってアカデミー賞などの主要部門を独占しているという話を聞いているからっていうのもあるよね?」
亀「知識が邪魔になってしまうことの好例じゃな」
映画の歴史を巡る旅
そして物語は2人の恋愛を描きながらも、たくさんの映画を思わせるオマージュシーンを重ねて作っているね
ここから映画の歴史を巡る旅が始まるのじゃよ
カエル「映画の歴史を巡る旅?」
亀「映画の歴史を紐解くと、もともとは音の鳴らないサイレント映画が主流の時代もあったわけじゃ。その時代、人々は劇場で静かな音のしない映画を見ていたと思うじゃろ? 実はそうではない。
劇場には伴奏者がおって、その人がピアノなどで演奏をしながら映画を鑑賞していたわけじゃ。お気に入りの伴奏者がいるから、その映画館に通うという人もおったようじゃの。それもトーキー映画が主流になるにつれて演奏する場所をなくしていき、姿を消していったがの。
日本では活弁士と呼ばれる人がおって……これは現代でも少しながら存在しておって、山崎バニラなどが有名かの。とにかく、映画に対して音をつけるのは劇場側の仕事であり、そこで様々な個性が生まれたわけじゃな」
カエル「みんなが同じ印象を受ける映画にはならないし、監督とかも制御が難しくなるけれど、そういう時代もあったんだね」
亀「その時代を象徴しておるのが、セバスチャンという存在じゃ。
彼はずっとジャズの話をしておるようじゃが、実は『ジャズ=映画』という風に変換しても話は通じる。いわばサイレント映画の時代に劇場で弾いていた伴奏者が、その仕事場をなくしていく、ということすらも表しておるわけじゃな」
カエル「へぇ……そこまで深読みできるんだ」

ジャズの話は映画の話へ……
(C)2016 Summit Entertainment, LLC. All Rights Reserved.
トーキーからサイレントへの懐古
それを象徴するシーンが、もしかして中盤のあの音無の……予告編にも使われている天文台の場面なわけ?
あのシーンは美しかったのぉ
亀「ミアはある瞬間、スピーカーを見つめてそこから流れる音楽を聴いて何かに気がつくじゃろ?
あれは何かというと、わしは『音楽演出の移り変わり』を表していると思う。つまり、それまで劇場で聞いていた音楽が……ピアノの音が、スピーカーから流れてくるようになった。そのことがサイレントからトーキー映画への移り変わりを意図している。
じゃがな、この映画は基本的に保守的すぎるほどに懐古主義の映画じゃ。じゃから、そのあとでわざと声を出さず、無言で踊るミュージカルのシーンを描き出し、まるでサイレント映画のような雰囲気を出したと言えるの」
カエル「ふ〜ん……そう考えると、そのちょっと前の駐車場でのミュージカルシーンも何か意味があるように思えてくるね」
亀「本作において『ミア=女優=映画の絵』だとしたら『セバスチャン=音楽=映画音楽』の象徴ということもできる。
この2人が少しずつ仲良くなっていく場面があの駐車場での場面であろうが、わしの記憶が確かなら、あの場面は『雨に唄えば』のオマージュがあったはずじゃ。
雨に唄えばという作品のテーマは『サイレントからトーキーへの移行』というものじゃったろ? これを考えると、その場面は『映画と音が初めて出会い、最初は喧嘩をしながらも徐々に楽しい映画を作り上げていった』という意味にも受け取れるわけじゃな」
カエル「色々考えられているんだねぇ……」
なぜこの映画は『ジャズ』なのか?
え? この映画がジャズの理由?
例えば時代に取り残された音楽ならば、別にジャズである必要はないじゃろ?
亀「クラシックなどもあるし、音楽のジャンルは多種多様じゃ。それこそフォークソングでもいいかもしれんの。
では、なぜこの映画は『ジャズ』の映画になっておると思う?」
カエル「え? 普通に考えればチャゼル監督がジャズを専攻したいたからじゃないの?」
亀「それは感想としてはありじゃが、批評としてはイマイチじゃの。
世界最初のトーキー映画は『ジャズシンガー』という作品じゃった。『お楽しみはこれからだ』という言葉が映画の世界に初めて取り入れられ、そしてジャズが流れることでトーキー映画の歴史は始まったとされておる。
映画音楽の歴史はジャズとともに始まったのじゃ。
じゃから、この映画においてジャズについて語ることは、そのまま映画音楽について語ることでもある」
カエル「へぇ! そうなんだ!」
亀「映画の冒険の旅はジャズと切っても切れない関係にある。
じゃから、この映画の中で何度も何度もジャズについて語っておるが、それは『映画音楽』について語っているからでもある。
例えば『伝統に縛られたままでいいの?』というのは、映画の音楽のあるべき形について語っているようでもあるし、さらに言えばミュージカル映画ってこんなにクラシカルなものばかりでいいの? ということでもある。現代でいえばヒップホップのミュージカル映画もあっていいわけじゃからな」
カエル「そういうことにも言及した映画なんだね」
![【初回生産限定】ジャズ・シンガー ワーナー・ブラザース90周年記念エディション [Blu-ray] 【初回生産限定】ジャズ・シンガー ワーナー・ブラザース90周年記念エディション [Blu-ray]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51fIsXJGpGL._SL160_.jpg)
【初回生産限定】ジャズ・シンガー ワーナー・ブラザース90周年記念エディション [Blu-ray]
- 出版社/メーカー: ワーナー・ホーム・ビデオ
- 発売日: 2013/01/18
- メディア: Blu-ray
- この商品を含むブログを見る
世界最古のトーキー映画とも言われるジャズシンガー。

- アーティスト: サントラ,ジャスティン・ハーウィッツ feat.エマ・ストーン,ジャスティン・ポール,ジャスティン・ハーウィッツ
- 出版社/メーカー: ユニバーサル ミュージック
- 発売日: 2017/02/17
- メディア: CD
- この商品を含むブログを見る
本作のサントラも素晴らしい!
映画館のミアのシーンについて
1部のファンからヘイトを集めているシーンだよね、ここ。
あれは実は重要なシーンであると考える
亀「わしもあのシーンはさすがにどうかと思ったがの……本当にあれをやられたら、怒るどころの話ではない。
じゃが、あれはあの時のミアを象徴するシーンでもある」
カエル「というと?」
亀「あの時のミアはどれほど望んだとしても、その映画の中には入れないわけじゃ。
結局は映画を外側から眺める観客でしかないわけで……映写機越しに映画に映るしかないと言うことを表しておる。
じゃがな、あのシーンにおいてミアはまだ『映画の中に入りたい』という情熱は持ち続けておるんじゃよ。それを象徴するのが、あのシーンということじゃな」
カエル「だから観客が誰も怒らないんだね」
亀「この作品は現実と地続きになっている『映画について語った映画』じゃからな。まあ、ここで冷めてしまういう反応は当然のものじゃろう。
唯一の失敗じゃと思う。ここでは観客は当然スクリーンを眺めているわけで、この状況に実際になったら? という現実に戻す要素を作ってしまったからの。それは必要なかったかもしれん」
ラストシーンの解釈について
解釈1 男女の恋愛観の差説
じゃあ、ラストシーンの解釈だけど! ここは僕も1つ解釈があるんだよね!
ほう……では語ってみるがいい
カエル「あれってさ、やっぱり男女の恋愛観を描いていると思うんだよ。男はいつまでも過去の女を思い出して、ずっとその女が自分のことを思い出しているように思うけれど、女はさっさと新しい男を見つけるっていうあるある話!
色々な映画にも使われているやり方で、そこを幻想的なムードとともに表すことであのラストになったんじゃないかな?」
亀「感想としてはいいかもしれんが、批評としてはイマイチじゃな」
カエル「えー!? 今回その意見多すぎない!?」
亀「本作は様々な解釈ができるからの。
では、次はわしの解釈じゃ」
解釈2 セバスチャン=チャゼル説
わしの解釈を話すとしよう
亀「まず、やはりセバスチャンというのはチャゼル監督の理想の姿ということができる。
夢を諦めずに追い続けて、それを叶えるわけじゃろ? その姿そのものがチャゼルの『こうありたかった姿』ということもできるわけじゃな。
以前、セッションの記事で主が『チャゼルはまだ諦めていない気がする』と語っておったが、今回でもやはりその夢を叶えることは諦めておらん。じゃが、その夢を追うことによる代償なども莫大なものであり、それを描いてきた監督でもあるわけじゃな」
カエル「その夢と代償があのラストなの?」
亀「自分を投影したキャラクターというのは、多くの監督や表現者が死なせたり、不幸な目に合わせたりするものじゃ。なぜならば『美しい死』や『切ないラスト』というのは、自己陶酔の極みとも言える。
自分を投影させるならば、ハッピーエンドにすると思うじゃろ? じゃがな、創作者というのはそうではない。
むしろ、その存在を不幸に落とすことで自分の今までの苦労や悲しみを代わりに背負ってもらって、消化してもらうのじゃ。あとは……単純にハッピーエンドすると恥ずかしいから、というのもあるかもしれんの」
カエル「なるほどね。だからあの物悲しいわけだ」
亀「あとは単純に夢破れたチャゼルの思いを代弁しておるということもできるが……これだけの作品を作っておいて、何が不満なのかはよくわからんがの」
カエル「それは完成して、その結果を知っているから言えることだけどね」

welcome to MOVIE world!
(C)2016 Summit Entertainment, LLC. All Rights Reserved.
解釈3 welcome to MOVIE world!
カエル「さて、ここでいよいよ主メモの登場だよ!」
亀「主はどんな解釈をするじゃろうな」
この映画は映画について描いた映画である!
【この映画は『映画について描いた映画である』ということは何度も書いてきた。
あのジャズバーというのは、その前の壁に描かれた観客席でもわかるように『映画の世界』である。
私は前回の感想記事で『セッション』が極めて重要だと語っていたが、その理由がここにあるのである。
セッションにおいてJKシモンズは鬼教師を演じており、それについていくものだけがたどりつける境地を描いていた。一方、ラ・ラ・ランドはJKシモンズに追い出された者が主人公の映画ということもできるわけである】
カエル「まあ、確かにね。才能がないわけではないけれど、勝手なことをして追い出されちゃう描写もあるわけだし……」
【そんなJKシモンズが『どうぞ』と合図をして店に入っていくシーンから幻想的なパレードは始まっていく。
ここでシモンズの役割というのは『映画の番人』である。夢を叶えられない者、まだその技量にいるべきでない者はここで弾く。しかし、女優として成功したミアと、夢を叶えたセバスチャンであればその資格は十分にあるわけだ。
映画の世界に入った2人は様々な映画的な体験をしていく。その幻想的なシーンに彩られながら、この映画はクライマックスを迎える。
だが、忘れてはならない。この映画はあくまでも『映画』であり『現実ではない』ということだ】
カエル「これって主がよく語ることだよね。映画と現実についての差」
【つまり、どれほど幻想的であろうと、美しかろうとそれは『映画』でしかないのである。
映画は映画である。現実ではない。そこを混合してしまうことは、極端なことを言えば妄想の世界で生きることにさせてしまいかねない。
特に本作はスタートにおいて強烈な形で『映画の世界』に没入させたのだから、現実に帰す作業というのは絶対に必要であり、それは製作者の義務であるとまで言えるだろう。だから、どれほどまでに素晴らしいと思っていても、それはやはり映画の世界、空想の世界ということを美しく示したのだ。
この作業において、本作の『映画の旅』というものは完成し『映画について語った映画』という本作は他作品と差をつけることに成功した】
亀「以上じゃな。
まあ、主が好きそうな論理じゃの」
カエル「いつも『映画と現実』ということは語るからねぇ……リアルVS空想の戦いかぁ……あれ? それってどこかで聞いたような……」
シンゴジラとラ・ラ・ランド
もしかして、主が『シン・ゴジラ』との類似性を指摘していたのってそういうこと?
それもあるかもしれんの。では、主メモもまた読んでみるかの
【本作に最も近い映画を問われた何か、と言われたら、私は『シン・ゴジラ』だと答える。
なぜならばシンゴジラという作品は私の解釈になるが、過去の特撮映画の要素を多く取り入れて、そしてそれを見事に1本の映画として消化し、特撮映画、そして日本というものを語った映画ということができるからである。
例えばシンゴジラの中では様々な過去の名曲たちが使われている。それはスタートのゴジラの鳴き声もそうであるし、宇宙大戦争などの名曲も非常に熱い場面で流れるわけである。
さらに言えば、スタートも初代ゴジラをオマージュしたものであり、他にも様々な場面でゴジラシリーズを連想させるように作られている。そういった小さな『オマージュの積み重ね』により、多くの特撮映画、特にゴジラについて総括し、そしてそれを更新した映画でもあるのだ」
カエル「確かにそんなことを語っていたね。色々と評判のいい記事だから、是非とも読んでもらいたいね」
【ではこのラ・ラ・ランドに話を戻すと、やはり類似する場面は多々見受けられるのである。
例えばスタートのタイトルロゴというのは全く同じ効果を発揮しているし、音楽や数々の映画のオマージュを積み重ねることにより、この映画は『映画を語る映画』として完成されていく。その手法は過去の作品の音楽やオマージュを積み重ねたシンゴジラと共通するものである。
また、スケール感も同様だろう。ゴジラは『特撮映画と東京』を描いたことに対して、本作は『(ミュージカル)映画とハリウッド』を描くことに成功した。
数少ない違いがあるとすれば、それはシンゴジラが過剰なまでに未来志向だったことに対して、本作は懐古的なシーンが多く見られることだろうか。ラストの終わり方なども、結局セバスチャンは革命者になることはできず、古いジャズとともにお店の中で終えることを選んだのである。そこは違いとしてあるかもしれない】
否定できない映画へ
【だが、そんな差など実はそう大したことではない。
本作においても最も重要なのは『作り手と観客の関係』である。
シンゴジラというのは庵野秀明が多くの観客のために作った映画である。これは言い換えると『オタクの、オタクによる、オタクのための映画』を完成させたということもできる。
そしてそれは本作も同じである。本作はそういった懐古的な映画も愛好する、映画ファンの中でもとりわけコアなファンに多く突き刺さっている。
つまりこの映画はチャゼルという映画オタクが贈る『映画オタクの、映画オタクによる、映画オタクのための映画』である。
なので、この映画は映画が好きであればあるほど、特に多くのミュージカル映画を愛好する者ほど否定できない映画となっているのである】
カエル「ふ〜ん……」
【ここでシンゴジラと違うのは、シンゴジラはやはりどれほど大きな影響力があろうとも『特撮映画』という映画界の中では決して主流とは言えない分野を総括した映画だった。なので、その熱量に対して、映画賞などはあまり注目をしていないという印象がある。
だが、本作は『ミュージカル映画』というハリウッド映画の中ではかなり注目度も高い分野を扱った映画であり、それを総括し、内包してしまった。
このスケール感の大きさというのはハリウッドの住人たちは驚愕であろうし、単なる楽しいエンタメで終わっていない。
だからこそ本作は大きな注目を集めるのである】
亀「以上じゃ。
ふむ……なるほどの。好きであるほど否定ができない映画という意味ではシンゴジラと共通しておるかもしれんの」
カエル「いつも主がいう『うまいより好き』っていうのは、こういうことなのかもしれないね。好きの力の大きさを改めて思い知ったよ」
最後に
いやー! 長い記事になったね!
最近は記事がどんどん長くなっていく傾向にあるの……これは分割しなかったら2万文字は超えておるぞ
カエル「なんか文字数主義をやめようか、と言っておきながら、違う意味での文字数主義になっていくような気がするね……」
亀「ちなみに、主メモにはこの映画にノレなかった理由も書いてあるので簡単に紹介するぞ
【夢追い人への応援歌っていうけれど、この2人は最初からある程度実力はあるから、あとは運の問題だろう。そこが求めていたものと違った印象。
やっているテーマは『SHIROBAKO』や『リトルウィッチアカデミア』などの夢追い人応援歌と同じであるが、この手の作品が『最初はダメダメだったものが成長していく』というお話に対して、本作は最初から技術面では完成されており、あとはチャンスを掴むだけという映画になっていた。
もちろん、そのチャンスを掴むというのが1番難しいのは重々承知しているが、そこが私の好きな作品と違って、少し肩透かしを食らった】
とのことじゃ」
カエル「まあ、個人の好みってことだろうね」
亀「さて、結構長くなってしまったし、ここで終了にするかの。
今回は疲れたのぉ……あとはどれだけ読まれるか、じゃな」
カエル「じゃあ今回の批評はここでおしまい! また次回ね!」
作品賞を受賞した『ムーンライト』の紹介はこちら!
今回出てきた映画達の記事はこちら
映画はこちらで購入できます
![シング・ストリート 未来へのうた スタンダード・エディション [Blu-ray] シング・ストリート 未来へのうた スタンダード・エディション [Blu-ray]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/510IYh+LYZL._SL160_.jpg)
シング・ストリート 未来へのうた スタンダード・エディション [Blu-ray]
- 出版社/メーカー: ギャガ
- 発売日: 2017/02/02
- メディア: Blu-ray
- この商品を含むブログ (1件) を見る


![セッション コレクターズ・エディション [Blu-ray] セッション コレクターズ・エディション [Blu-ray]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/41pUvgdZHBL._SL160_.jpg)
